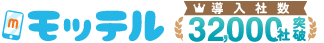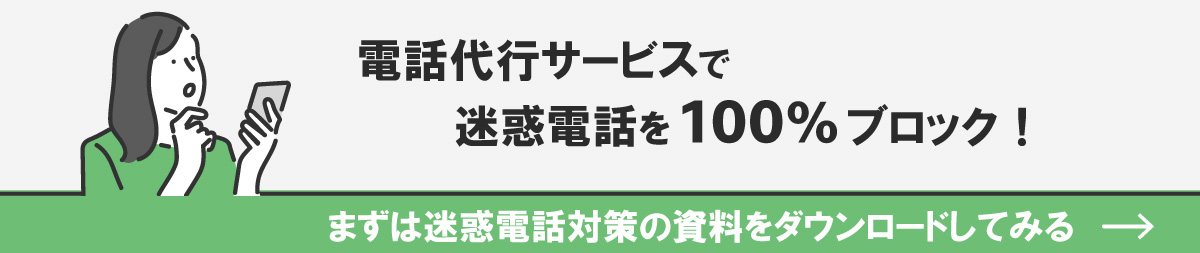求人広告のしつこい営業電話にうんざりしていませんか?効果的な対策とツールの活用方法を解説
最終更新日:2025年12月2日

「〇〇求人メディアの〇〇と申します。現在、ご採用の状況はいかがでしょうか?」
企業や店舗が求人を出すと、なぜか一斉にかかってくる営業電話。企業の経営者や人事担当者であれば、このフレーズから始まる電話に一度は頭を悩ませたことがあるのではないでしょうか。日々の業務に追われる中で、鳴り響く求人広告の営業電話。断っても、手を変え品を変え、繰り返しアプローチしてくるその執拗さに、うんざりしている方も少なくないはずです。
また最近では電話で「無料で当社のサイトに求人広告を掲載しませんか?」との勧誘があり、契約したところ、無料掲載期間経過後に自動で有料掲載へ移行し、多額の広告料金を請求される(「ハローワーク求人掲載時の営業電話のトラブルにご注意ください」より)といった事案が発生しています。
この営業電話は、貴重な時間を奪うだけでなく、業務への集中を妨げ、精神的なストレスの原因にもなります。本来、企業の成長に不可欠な「採用活動」をサポートするはずのサービスが、なぜこれほどまでに担当者の負担となっているのでしょうか。
この記事では、年間数百件もの営業電話に対応してきた筆者の経験と知見に基づき、求人広告の営業電話に悩むすべての担当者に向けて、求人広告営業の電話がなぜかかってくるのか、その対策方法、そして導入すべきツール、さらには二度とかかってこないようにするための仕組み作りまで徹底的に解説します。
この記事を読み終える頃には、あなたは営業電話に対する漠然としたストレスから解放され、毅然とした態度で対応できるスキルを身につけているはずです。そして、本来注力すべきコア業務や、より戦略的な採用活動に時間とエネルギーを投下できるようになるでしょう。
- コンテンツの目次
求人広告の営業電話はなぜこんなに多いのか?その背景とカラクリ
効果的な対策を講じるためには、まず敵を知ることから始める必要があります。 なぜ、求人広告の営業電話はこれほどまでに頻繁で、そしてしつこいのでしょうか。 その背景には、求人広告業界特有の構造と、営業担当者が置かれた厳しい環境が存在します。
1. 熾烈な競争が生む「数打てば当たる」営業
現在の日本には、大手から中小、特定の業種や職種に特化したものまで、数えきれないほどの求人媒体が存在します。インターネットの普及により、誰もが比較的容易に求人情報サイトを立ち上げられるようになったことも、その数を押し上げる一因となっています。
媒体が増えれば、当然、企業という限られたパイを奪い合う競争は激化します。多くの求人広告会社にとって、収益の柱は広告の「掲載料」です。採用が成功したかどうかにかかわらず、広告を掲載した時点で売上が発生するビジネスモデルが主流であるため、各社はとにかく自社の媒体に広告を掲載してくれる企業を一つでも多く見つけようと必死になります。
この熾烈な競争環境が、「質より量」「数打てば当たる」という営業スタイルを助長しているのです。
2. 営業担当者に課せられる厳しいノルマ
多くの求人広告会社の営業担当者には、厳しいノルマが課せられています。その内容は、単に契約数や売上目標だけではありません。
- テレアポ件数: 1日に100件、200件といった架電数が目標として設定されているケースは珍しくありません。
- アポイント獲得数: 電話でアポイントを取り、商談の機会を得ることも重要な指標です。
- 新規顧客獲得数: 既存顧客だけでなく、常に新しい顧客を開拓し続けることが求められます。
これらのノルマを達成できなければ、評価や給与に直接影響します。そのため、営業担当者は「断られても次」「とにかくかけ続ける」という行動を取らざるを得ない状況に追い込まれているのです。彼らもまた、会社のシステムの中で必死に業務を遂行しているにすぎない、という側面も理解しておく必要があります。
3. どこから入手?企業リストのからくり
「なぜ、うちの会社の電話番号を知っているんだ?」と不思議に思ったことはありませんか。営業担当者が利用する企業リストの入手元は、主に以下の通りです。
- 公開情報: 企業の公式ウェブサイト、会社登記情報、過去に掲載された求人広告、業界団体の名簿など、一般に公開されている情報からリストを作成しています。特に、過去に一度でも求人広告を出したことがある企業は、「採用ニーズがある企業」としてリストアップされやすくなります。
- リスト専門業者からの購入: 企業情報を取りまとめて販売している専門業者から、リストを購入するケースも一般的です。これらのリストは複数の広告会社に渡って使い回されるため、同じ会社から担当者を変えて何度も電話がかかってきたり、異なる広告会社から同じタイミングで電話が集中したりする現象が起こるのです。
一度リストに載ってしまうと、半永久的に様々な会社から営業電話がかかってくる可能性がある、というわけです。
4. 断りきれない心理を突く営業テクニック
しつこい営業電話は、単に回数が多いだけではありません。担当者が断りにくい状況を作り出す、巧妙な心理的テクニックが使われていることもあります。
- 緊急性を煽る: 「このエリアで急募の企業様向けの特別キャンペーンが本日まででして…」「御社が求めるような優秀な人材は、すぐに他社に決まってしまいますよ」といった言葉で、担当者の「機会損失をしたくない」という心理を刺激します。
- 罪悪感に訴えかける: 「ほんの3分で結構ですので、お話だけでも…」「お忙しいところ大変恐縮ですが…」と低姿勢で切り出し、断ることに罪悪感を抱かせようとします。
- 担当者との関係構築を狙う: 「〇〇様のお声だけでもお聞かせいただければ…」と、あたかも個人的な関係性を築こうとするようなアプローチで、情に訴えかけます。
これらのテクニックに惑わされ、曖昧な返事をしてしまうと、「脈あり」と判断され、さらにしつこい電話を招く原因となってしまいます。
求人広告の営業電話がもたらす3つの業務的デメリット
1. 業務が中断されるストレス
営業電話は、通常業務を行っている中で突然かかってくるため、集中力が途切れたり、会議や接客中に出ざるを得なかったりと、生産性を低下させる原因になります。
2. 対応コストが増える
内容を確認して、断るために数分~10分近くかかる場合も。さらに何度も同じ会社からかかってくるケースもあり、社内での対応マニュアル作成なども必要になってしまうことも。
3. スタッフやアルバイトが対応し、トラブルに
中小企業や飲食店では、代表番号にスタッフが出るケースもあります。営業電話に対応した結果、個人情報や採用状況を無意識に漏らしてしまい、トラブルになることもあります。
【実践編】求人広告の営業電話をスマートに撃退する具体的な断り方フレーズ集
相手の背景を理解した上で、次はいよいよ具体的な撃退方法です。重要なのは、「毅然と、しかし丁寧に」断る姿勢です。感情的になったり、高圧的な態度を取ったりすることは、企業の評判を損なうリスクがあるため避けましょう。ここでは、あらゆるシーンを想定した実践的なフレーズをご紹介します。
基本姿勢:曖昧さは最大の敵!「検討します」は禁句
営業電話を撃退する上で、最もやってはいけないのが曖昧な態度です。「まあ、一応検討してみます」「また機会があれば…」「資料だけ送ってください」といった返答は、相手に期待を持たせるだけです。営業担当者は、その言葉を「見込みあり」のサインと捉え、必ずと言っていいほど再度アプローチしてきます。
断る際は、明確な意思表示が必要です。しかし、それは無礼な態度を取るということではありません。丁寧な言葉遣いを保ちながら、きっぱりと断ることが、自社の品位を保ちつつ、相手に「これ以上は無駄だ」と理解させる最善の方法です。
シーン別・相手別 断り方フレーズ集
1. 初回電話の断り方(基本形) 最も使用頻度の高い、基本的な断り方です。このフレーズを覚えておくだけで、大半の営業電話は撃退できます。
「お電話ありがとうございます。大変申し訳ございませんが、現在、求人広告の利用は一切検討しておりません。今後、必要になった際には、こちらから改めてご連絡させていただきますので、今後の営業のお電話はご遠慮いただけますでしょうか。」
ポイント:
・「検討していない」と明確に伝える。
・「こちらから連絡する」と伝え、相手からのアプローチを遮断する。
・「今後の電話は遠慮する」と釘を刺す。
2. すでに取引のある媒体が決まっている場合 他社を利用していることを伝えるのも有効な断り方です。
「ありがとうございます。ただ、採用活動に関しましては、お付き合いのある会社様一社にお任せしておりますので、他社様からのご提案はすべてお断りしている状況です。申し訳ございません。」
ポイント:
・「すべてお断りしている」という社内ルールであることを示唆することで、相手が食い下がる余地をなくします。
3. しつこく食い下がられた場合の対応 一度断っても、「なぜですか?」「どこかお困りではないですか?」などと食い下がってくる営業担当者もいます。その場合は、少し語気を強め、しかし冷静に対応します。
「先ほどもお伝えいたしましたが、現在は必要としておりません。これ以上のお話はできかねますので、失礼いたします。」
(さらにしつこい場合)
「大変恐縮ですが、これ以上の営業活動は当社の業務の妨げとなります。今後のご連絡は固くお断りいたします。お電話番号を弊社のリストから削除していただけますでしょうか。」
ポイント:
・「業務妨害」という言葉を使い、相手の行為が迷惑であることを明確に伝える。
・「リストからの削除」を具体的に要求する。
4. 「担当者の方をお願いします」と言われた場合 受付担当者や電話に出た社員が、「採用担当の〇〇をお願いします」と名指しで要求されるケースも多いでしょう。安易に取り次ぐのは絶対にやめましょう。
「どのようなご用件でしょうか?」(用件を聞いた上で)
「あいにくですが、〇〇(担当者名)は現在、他の業務で手が離せません。また、求人広告に関するご案内は、すべてお断りするように申し付かっておりますので、お繋ぎすることはできません。ご了承ください。」
(担当者名がわからない場合)
「恐れ入りますが、担当者の個人名はお伝えできかねます。ご用件をお伺いいたします。」
ポイント:
・必ず用件を確認する。
・「担当者の指示で断っている」という形にすることで、電話に出た人が断りやすくなる。
5. 「資料だけでも送らせてください」と言われた場合 これもよくある手口です。資料を送らせてしまうと、それを口実に「ご覧いただけましたでしょうか?」という確認の電話がかかってきます。
「ありがとうございます。ただ、お送りいただいても、現状では拝見する時間がございませんので、今回はご遠慮させていただきます。お気持ちだけ頂戴いたします。」
ポイント:
・「時間がない」という物理的な理由を伝え、丁重に断る。
・「お気持ちだけ頂戴します」の一言で、相手への配慮を示し、話を終わらせやすくする。
営業電話をかけてこさせないための「魔法の言葉」
時には、より強く相手を牽制する言葉が必要になることもあります。以下のフレーズは、相手に「この会社は手強い」と思わせる効果が期待できます。
「今後の営業活動の参考にさせていただきたいのですが、弊社の情報はどちらのリストから入手されましたか?」
情報源を問うことで、相手はうかつな発言ができないと身構えます。個人情報保護やコンプライアンス意識が高い企業であるという印象を与えることができます。
「特定商取引法に基づき、再勧誘の禁止をお願いします。」
特定商取引法では、事業者が電話勧誘で一度断られた相手に対して、再勧誘することを禁止しています。この法律の名前を出すことで、相手に法的なプレッシャーをかけ、今後の連絡を躊躇させることができます。
「弊社の社内規定により、お電話での新規営業はすべてお断りしております。お問い合わせフォームからご連絡ください。」
「会社のルール」という、個人的な感情ではない理由を盾にすることで、非常に断りやすくなります。実際にWebサイトにお問い合わせフォームを設置し、そこに誘導するのも有効です。
これらのフレーズを状況に応じて使い分けることで、あなたは営業電話の主導権を握ることができるようになります。
もう電話を鳴らさせない!営業電話を根本からなくすための仕組み作り
その場しのぎの対応だけでなく、営業電話そのものを減らすための「仕組み」を社内に構築することが、根本的な解決への道です。ここでは、今日から始められる具体的な施策をご紹介します。
1. 社内での「統一ルール」の徹底と情報共有
最も重要なのが、社内での対応ルールを統一することです。誰が電話に出ても同じ対応ができるよう、具体的なマニュアルや対応スクリプトを作成し、全社員で共有しましょう。
マニュアル作成:
前章で紹介したような断り方フレーズをまとめる。
「担当者には絶対に取り次がない」「用件を聞いて『求人広告』と判断したら、マニュアル通りに対応する」といった基本方針を明記する。
特に、電話応対の機会が多い受付担当者や新入社員には、重点的に研修を行う。
情報共有:
しつこい業者の会社名や電話番号を、社内のチャットツールや共有ファイルなどでリスト化する。「要注意リスト」として共有することで、他の社員が同じ苦労をせずに済みます。
このルール作りによって、「〇〇さんなら話を聞いてくれるかもしれない」という営業担当者の淡い期待を打ち砕き、会社全体として営業を拒否する姿勢を明確に示すことができます。
2. 会社のウェブサイトに「防壁」を設置する
企業の公式ウェブサイトは、営業担当者が最初にチェックする情報源の一つです。ここに、営業電話を牽制する一文を記載しておくだけで、一定の効果が期待できます。
「営業お断り」の明記:
「会社概要」「お問い合わせ」「採用情報」といったページに、**「求人広告やその他サービスに関する営業のお電話は、業務の妨げとなりますので固くお断りいたします。」**といった文言を目立つように記載します。
「問い合わせフォームの活用:
会社の代表電話番号の掲載を最小限にし、問い合わせは原則としてウェブサイト上の「お問い合わせフォーム」に誘導するフローを構築します。フォームには「営業目的での利用を固く禁じます」と注意書きを添えましょう。これにより、電話番号のリスト化を防ぐとともに、営業メールをフィルタリングしやすくなります。
3. テクノロジーの力を借りる(電話システムの活用)
現代では、テクノロジーを活用して迷惑電話をシャットアウトする方法も充実しています。
迷惑電話ブロックサービスの導入:
多くのビジネスフォンやクラウドPBXには、特定の電話番号からの着信を拒否する機能が搭載されています。しつこい業者の番号は、躊躇なく着信拒否設定しましょう。
また、警察や自治体から提供される迷惑電話番号リストをもとに、自動で着信をブロックしてくれるサービスもあります。
| サービス名 | 内容 |
|---|---|
| MOT/TEL | 全社員共通の着信拒否機能で簡単に迷惑電話を拒否。 |
| トビラフォン | 警察・自治体など、公的機関による情報を反映した迷惑電話フィルタ。 |
| INNOVERA | 電話番号の前方一致による着信拒否設定機能と、最新の着信履歴から2ステップで着信拒否。 |
IVR(自動音声応答)システムの活用:
「〇〇株式会社です。お電話ありがとうございます。採用に関するお問い合わせは1番、製品に関するお問い合わせは2番を…」という、あのおなじみのシステムです。
この冒頭のアナウンスに、**「なお、求人広告等の営業に関するお電話は、担当部署へお繋ぎできませんのでご了承ください。」**という一文を付け加えるだけで、多くのテレアポ担当者はその時点で電話を切るでしょう。電話を取る前に相手をふるいにかける、非常に効果的な手法です。
これらの仕組みは、一度導入してしまえば継続的に効果を発揮し、担当者の心理的・時間的負担を大幅に軽減してくれます。
| サービス名 | 内容 |
|---|---|
| MOT/TEL | 最大99個まで吹き込めるアナウンス。全ての通話を自動録音、文字起こしできる機能もあり。 |
| IVRy | IVR機能を標準搭載。3,480円/月〜+ 通話代(税抜)から使える。 |
| Visual IVR | WebブラウザにデザインされたIVRメニューを表示、チャットボットやFAQに誘導。 |
電話代行サービスの活用: 電話の一次対応を外部に委託することで、営業電話をブロックできます。受けた電話の内容はメールやチャットで知らせてくれるため、必要な電話だけに対応し、不要な電話対応を減らす効果が期待できます。
| サービス名 | 内容 |
|---|---|
| オフィスのでんわばん | 全ての通話を自動録音。いつでも再生。契約期間の縛りなく自由に使える。 |
| fondesk | 電話のお知らせの通知先としてさまざまなサービスに対応。 |
| Jream | 月額2,000円∼営業電話の課金なし。 |
それでも電話がやまない場合の最終手段と、知っておくべき注意点
これまでの対策を講じてもなお、悪質でしつこい営業電話が続く…。そんな場合の最終手段と、すべての営業電話を悪と決めつけないための注意点について解説します。
最終手段:法的措置と公的機関への相談
度重なる警告を無視し、業務に支障をきたすほどの悪質な営業電話に対しては、より強固な姿勢で臨む必要があります。
特定商取引法(特商法)の再勧誘の禁止:
前述の通り、特商法では、電話勧誘において契約しない旨の意思表示をした消費者に対し、事業者が再勧誘することを禁止しています。「断ったはずなのに、またかけてきた」という行為は、この法律に抵触する可能性があります。
公的機関への相談:
あまりに悪質な場合は、消費者庁や国民生活センター、管轄の経済産業局などに相談するという選択肢もあります。実際に指導や処分が行われるケースは稀ですが、「公的機関に相談する」という姿勢を見せること自体が、強力な牽制となり得ます。電話口で「これ以上続くようであれば、しかるべき機関に相談させていただきます」と伝えるだけでも効果があるでしょう。
ただし、これらはあくまで最終手段です。時間も労力も要するため、まずはこれまでの章で紹介した対策を徹底することが先決です。
注意点:すべての営業電話が悪とは限らない
ここまで営業電話を「撃退する」という視点で話を進めてきましたが、一つだけ心に留めておきたいことがあります。それは、すべての営業電話が悪ではないということです。
中には、自社の採用課題を的確に捉え、本当に価値のある情報や、思いもよらなかった採用手法を提案してくれる優秀な営業担当者も、ごく稀にですが存在します。例えば、以下のようなケースです。
- 自社の採用ターゲットに特化した、ニッチな媒体の提案。
- 採用市場の最新動向や、競合他社の採用戦略に関する有益な情報提供。
- 採用ブランディングに関する新たな視点でのコンサルティング。
もし、自社に明確な採用課題があり、情報収集をしたいと考えているフェーズであれば、無下に断るのではなく、「5分だけ」と時間を区切って話を聞いてみるという選択肢もゼロではありません。
ただし、その場合でも重要なのは、主導権は常にこちらが握ることです。「話を聞いてやっている」というスタンスを崩さず、相手のペースに乗せられないように注意しましょう。少しでも「これは自社のためにならない」と感じたら、「貴重な情報をありがとうございました。社内で検討させていただきます。必要であればこちらから連絡します。」と、こちらから話を打ち切ることが肝心です。
よくある質問(FAQ)
Q. 求人広告営業は違法ではないの?
A. 違法ではありませんが、しつこい・執拗な勧誘は「迷惑行為」に該当する可能性があります。
Q. 同じ会社から何度もかかってくる場合はどうする?
A. 電話番号を着信拒否に設定するか、電話代行・PBXなどで遮断対策を行いましょう。
Q. 求人広告を出しても営業電話を防げる?
A. 完全には防げませんが、非公開求人や受付代行の活用で最小限に抑えることができます。
まとめ|求人広告営業の電話に、時間と労力を奪われないために
求人を出した直後や定期的に、営業電話はどこからともなくかかってきます。
しつこい求人広告の営業電話は、多くの企業担当者にとって悩みの種です。しかし、その背景にある業界構造や営業担当者の事情を理解し、正しい知識と具体的なテクニックを身につけることで、その悩みは必ず解消できます。
今回ご紹介した対策を、最後にもう一度おさらいしましょう。
- 毅然と、しかし丁寧に断る: 「検討します」は禁句。明確な言葉で、しかし礼儀正しく断る姿勢が基本です。
- 仕組みで対策する: 個人の頑張りに頼るのではなく、社内ルールを統一し、ウェブサイトや電話システムを活用して、営業電話がかかってきにくい環境を構築しましょう。
- 主導権を握る: 話を聞く場合でも、時間を区切り、常にこちらが主導権を持つことを忘れないでください。
これらの対策を実践することで、あなたは日々の煩わしい営業電話から解放され、年間で数十時間、あるいはそれ以上の貴重な時間を取り戻すことができるはずです。その時間を使って、より企業の未来に繋がる戦略的な採用計画を練ったり、既存の従業員のエンゲージメントを高める施策に取り組んだりすることこそ、本来あるべき人事担当者の姿ではないでしょうか。
「うちは絶対に営業電話を取らない」という体制を作ることで、確実に削減可能です。
特に業務効率を重視する企業では、電話代行やクラウドPBXの導入が広まりつつあります。
煩わしい営業電話にもう悩まされない、そんな働きやすい職場づくりの一歩を、今こそ踏み出してみてはいかがでしょうか?