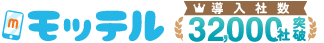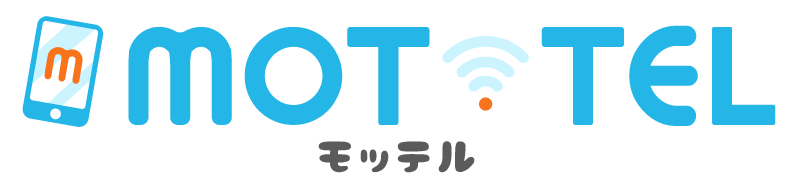昼休みの電話対応は違法?企業が守るべき休憩時間ルールと対策【チェックリスト付き】
最終更新日:2025年11月6日

昼休みにも電話対応を求められる -そんな職場は少なくありません。
しかし、労働基準法では「休憩時間中は労働から完全に解放されること」が原則とされています。つまり、昼休み中に電話対応をさせる行為は、場合によっては違法となる可能性があります。
本記事では、
・昼休み中の電話対応が「労働」とみなされる基準
・違法になるケースと合法とされるケースの違い
・企業が取るべき実践的な対策とチェックリスト
をわかりやすく解説します。
人事・総務担当者の方はもちろん、職場環境の改善を進めたい管理職の方にも役立つ内容です。
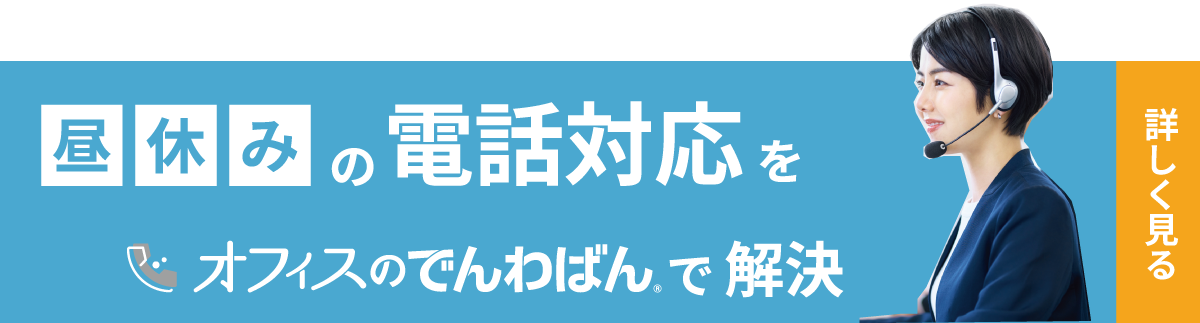
- コンテンツの目次
はじめに:昼休み中の電話対応がなぜ問題になるか
昼休みは、労働基準法で「労働者が自由に休息できる時間」として定められています。
しかし実際には、「昼休みでも電話が鳴れば取るのが当たり前」「交代制にしているから大丈夫」といった理由で、社員が休憩中に電話対応を行っている職場も少なくありません。
一見すると業務への協力のように見えますが、この“昼休み中の電話対応”は、法的には労働とみなされる可能性があり、企業側が労働基準法違反に問われるリスクもあります。
この問題は、企業のコンプライアンスだけでなく、従業員のモチベーション低下や離職につながる恐れもあるため、適切な運用ルールを整備することが重要です。
なぜ「昼休み対応」が放置されやすいか
多くの企業では、「業務が止まるのを避けたい」「電話番を誰かがしなければならない」という事情から、昼休みの電話対応が慣習化しています。
とくに少人数のオフィスや受付対応が必要な業種では、「たまたま近くにいた人が出る」「持ち回り制で対応している」といった曖昧な運用になりがちです。
さらに、「本人も特に不満を言っていない」「これまで問題にならなかった」という理由で、企業側がリスクを自覚していないケースも多く見られます。
しかし、こうした状態を放置すると、労働時間の管理不備や残業代の未払い、労基署からの指導につながる恐れがあるため、早めの見直しが必要です。
「休憩時間」の法律・制度の基礎知識
昼休み中の電話対応を考えるうえで、まず理解しておくべきなのが「休憩時間の定義」と「労働とみなされる範囲」です。
これらは労働基準法第34条に明確に規定されており、違反した場合には是正勧告の対象になることもあります。
労働基準法 第34条「休憩時間」の三原則
労働基準法第34条では、休憩時間について以下のように定められています。
労働基準法 第34条(休憩)抜粋
使用者は、労働時間が6時間を超える場合に少なくとも45分、8時間を超える場合に少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
さらに、この休憩時間には「三原則」があります。
①一斉付与の原則
原則として、同じ職場で働く労働者には同じ時間帯に休憩を与える必要があります。
ただし、交代制勤務など業務の性質上やむを得ない場合は例外が認められます。
②自由利用の原則
休憩時間中は、労働から完全に解放され、自由に利用できることが求められます。
この原則に反する状態(電話番・来客対応・上司の指示待ちなど)は、休憩とは認められません。
③労働時間の途中付与の原則
休憩は、勤務の前後ではなく労働時間の途中で与えなければなりません。
つまり、勤務開始前や終了後に「まとめて取る」ことは、休憩時間として扱われません。
待機時間/手待ち時間と休憩時間の違い
昼休み中に「電話が鳴ったら対応する」「上司から呼ばれるかもしれない」といった状況は、“休憩”ではなく“手待ち時間”に分類されます。
手待ち時間とは
労働者が一見休んでいるように見えても、使用者の指示にすぐ応じられる状態で待機している時間のことを指します。
たとえば、以下のようなケースです。
・電話が鳴ったら取るよう指示されている
・来客対応のために席を離れられない
・呼び出しがあればすぐ対応する体制にある
このような場合、労働の拘束下にあると判断されるため「労働時間」として扱われるのが原則です。
つまり、昼休み中に電話対応の義務がある場合、形式上は「休憩」としていても、実際には休憩時間として認められない可能性があります。
厚生労働省の見解・FAQ(公式見解)
厚生労働省の「労働基準法に関するQ&A」や行政解釈でも、以下のように明確に示されています。
Q:私の職場では、昼休みに電話や来客対応をする昼当番が月に2~3回ありますが、このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか。
A:ご質問にある昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。従って、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩を与えなければなりません。
(参考:厚生労働省webサイト 雇用・労働 > よくある質問)
また、同サイトに次のような注意喚起があります。
休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。
従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。
つまり、「形式的に昼休みを与えているだけ」では不十分で、実際に自由に休める環境を確保しているかどうかが重要な判断基準になります。
休憩時間中の電話対応が労働時間と認められるケース
昼休み中でも電話に出たり、上司の指示に対応したりしている場合、形式上は「休憩」としていても、実質的には労働時間と判断されることがあります。
ここでは、行政解釈や判例で示されている判断基準をもとに、どのような場合に「休憩」ではなく「労働」と認められるのかを解説します。
判例・行政解釈から見る判断要素
厚生労働省や裁判所は、休憩時間が「自由に利用できる状態であったかどうか」を最も重視しています。
つまり、実際に労働から解放されていたかが判断の分かれ目になります。
判断の主なポイント
以下のような要素が、労働時間と認められるかの判断基準になります。
| 判断要素 | 労働時間とされる可能性が高い例 |
|---|---|
| 使用者の指示・命令があった | 「電話が鳴ったら出るように」と明示されている |
| 呼び出し対応義務がある | 来客・取引先の連絡に備えて待機している |
| 職場から離れられない | 休憩中もデスク周辺にいる必要がある |
| 実際に業務を行っている | 電話対応・書類整理・顧客応対をしている |
参考判例
東京地裁 平成3年3月28日判決(日本システム技術事件)では、「呼び出しに応じる義務がある待機時間」は労働時間と認定されています。
このように、「形式的に休憩時間を与えている」だけでは不十分で、実質的に労働から解放されていなければ休憩時間とは認められないのが原則です。
休憩時間扱いできない具体例
実務でよく見られる「休憩時間として扱えないケース」を挙げます。
✖️休憩時間に該当しない例
・電話番や受付を担当しており、呼び出しがあれば対応する
・店舗の混雑状況により、休憩時間が不規則に変更される
・上司や同僚の依頼で事務作業を行う
・お客様対応のため、休憩室に行けずデスクで待機している
・「誰もいないと困るから」と暗黙の了解で電話を取っている
これらはいずれも「自由利用の原則」に反する状態であり、たとえ「休憩中」と名目をつけていても、実質は労働時間として扱われる可能性があります。
交替制休憩や一斉休憩免除の例外・条件
業種や業態によっては、全員が一斉に休憩を取ることが難しい場合もあります。
そのため、労働基準法では以下のような例外的な運用を認めています。
交替制休憩(シフト休憩)
店舗・コールセンター・受付業務など、常に人員を配置する必要がある職場では、交替制で休憩を取る運用が可能です。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。
・休憩中の労働者が完全に業務から解放されていること
・交替のタイミングが明確に管理されていること(就業規則やシフト表など)
・実際に交替が行われ、休憩が形骸化していないこと
一斉休憩の免除(労働基準法第34条第2項)
運輸業・警備業・販売業など、業務の性質上やむを得ない場合には、労働基準監督署への届出により「一斉休憩」の原則を免除することができます。
ただし、これも「休憩時間の自由利用が確保されていること」が前提です。
実践的な代替手段と運用方法
「昼休み中の電話対応をなくしたい」と考えても、現実的には取引先からの連絡や顧客対応が必要な企業も多いでしょう。
ここでは、法令を遵守しながら業務を止めないための代替手段と運用設計を紹介します。
電話代行サービス導入(PBX連携型サービスも含む)
昼休み中の対応を外部に委託する方法として、電話代行サービスの導入が効果的です。
コールセンターの専門オペレーターが代わりに一次対応を行い、重要な内容のみを担当者にメールやチャットで転送します。
利用料金も、電話対応人件費と見なせば導入しやすい価格設定のサービスが多くあります。
導入のメリット
・昼休み中も電話を取りこぼさない
・社員に休憩時間を取らせることができる
・顧客満足度を維持しつつ、内部リソースを確保できる
・アウトソーシングサービスを利用することで経費を抑えられる
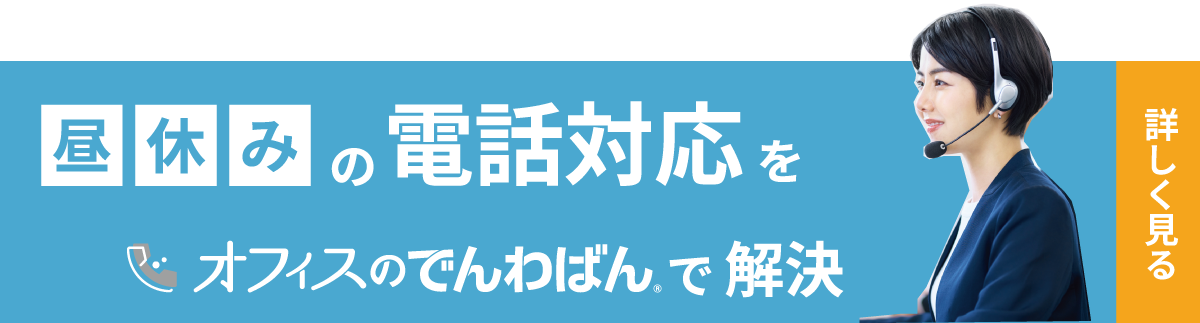
クラウドPBX連携型サービスの活用例
クラウドPBXとは、従来オフィスに設置していた電話交換機(PBX)の機能をクラウド上で提供するシステムです。
インターネットを介して通話を管理できるため、場所を選ばずに内線・外線の転送や録音、IVRなどを柔軟に運用できます。
このクラウドPBXと、電話代行サービスを連携することで、
・昼休み時間に自動で代行サービスへ転送
・通話内容を録音・テキスト化して担当者へ通知
・API連携により、kintone・SalesforceなどCRMと自動連携
といった効率的かつ法令遵守型の運用が実現しますのでおススメです。
IVR・自動応答による対応の工夫
昼休みの時間帯をあらかじめシステムで制御するのも有効です。
IVR(自動音声応答)での例
「現在、昼休憩中のためお電話がつながりにくくなっております。
ご用件をお伺いする場合は【1】、担当部署への折り返しを希望される方は【2】を押してください。」
このように設定すれば、電話を取らずに顧客対応を完結できます。
運用のポイント
・昼休憩時間をPBX側で自動設定(例:12:00〜13:00)
・録音・折り返し依頼をメールやチャットに通知
・必要に応じて、特定の番号のみ転送先を指定
こうした仕組みにより、「誰かが出ないといけない」状況をシステムで排除できます。
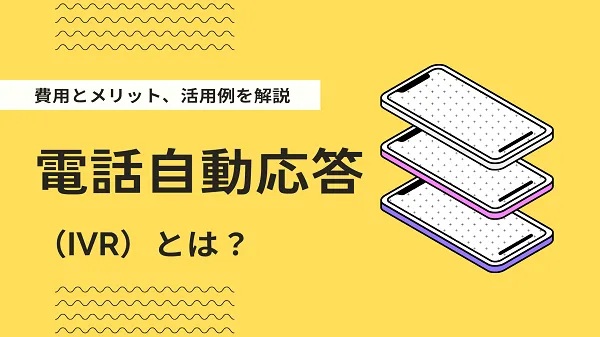
交替制/シフト制での休憩設計(就業規則・労使協定含む)
コールセンターや受付業務など、完全に電話を止められない業種では、交替制休憩が現実的です。 ただし、単に「当番制」にするだけでは法的に不十分な場合があります。
適法な交替制にするためのポイント
・就業規則に「交替制休憩を採用する旨」を明記
・労使協定で「一斉休憩免除(労基法34条2項)」の締結
・各従業員に実質的な休憩時間を確保(離席・外出可)
・シフト表や勤務記録で休憩実施を証明できるようにする
例文(就業規則追記例)
「業務の性質上、一部の部署では一斉休憩を実施しない。
各従業員には交替制により60分の休憩時間を与える。」
こうした明文化がないまま当番制を行うと、違法リスクを残す結果となります。
管理監督者や例外業種の活用が可能なケース
一部のケースでは、昼休み中に対応しても法的に問題とならない場合があります。
ただし、これらは限定的な例外に該当します。
管理監督者の場合
・労働基準法第41条に基づき、労働時間・休憩・休日の適用除外
・ただし「管理監督者にふさわしい権限・待遇」があることが条件
・実際には適用範囲が狭く、一般社員への適用は不可
例外業種(労基法施行規則第31条)
・交通運輸、医療、警備、接客など「業務の性質上やむを得ない職種」
・一斉休憩の適用を受けない業種でも、休憩の実施義務は残る
・実態として「交替で休める仕組み」を確保する必要あり
これらのケースも、「形だけの休憩」では認められない点に注意が必要です。
休憩時間を別に確保する方法
昼休み中にどうしても業務対応が必要な場合、別時間帯に休憩を振り替える運用を取り入れることで、法令遵守を維持できます。
例:振替休憩の設計
| 状況 | 対応策 |
|---|---|
| 12:00〜13:00に電話当番対応 | 14:30〜15:30を休憩に振り替える |
| 当番が10分ごとに対応 | 対応分を累積して、後に休憩補填 |
この方法を採用する場合は、
・就業規則で振替休憩を認める旨を明記
・勤怠システムで「休憩補填時間」を入力・記録
・本人に通知・承認を取る
といった運用上の透明性が求められます。
実務フォーマット・チェックリスト
昼休み中の電話対応問題を解決するためには、制度設計と運用の見える化が欠かせません。
ここでは、企業がすぐに活用できる「就業規則条文例」「労使協定テンプレート」「導入時チェックリスト」「モニタリング指標」を紹介します。
就業規則条文例(交替休憩規定など)
昼休憩の交替制運用を合法的に行うためには、就業規則に明文化しておくことが必須です。
以下は、法的要件を満たしつつ、柔軟な運用ができる記載例です。
就業規則・条文例
(休憩時間)
第○条 休憩時間は次のとおりとする。
1.原則として、12時から13時までの1時間を休憩時間とする。
2.業務の都合により、一斉に休憩を与えることが困難な部署については、交替制により休憩を与えることがある。
3.交替制による休憩時間の割当は、事前に管理者が勤務シフトにより定めるものとする。
4.交替制休憩を行う場合も、各労働者が実質的に自由な休憩を取れるよう配慮するものとする。
この条文をベースに、「昼休憩の当番制」「振替休憩の補填」「転送対応などの扱い」も併せて明文化すると、より実効性が高まります。
労使協定テンプレート(休憩一斉付与免除)
労働基準法第34条第2項では、原則として「休憩は一斉に与える」ことが定められていますが、 例外として「労使協定を締結すれば一斉でなくてもよい」とされています。
労使協定(サンプルテンプレート)
休憩時間の一斉付与免除に関する協定書
株式会社〇〇〇〇(以下「会社」という。)と、労働者代表△△△△(以下「代表」という。)は、労働基準法第34条第2項の規定に基づき、休憩時間の一斉付与を行わないことについて、次のとおり協定する。
第1条(対象労働者)
交替制勤務を行う〇〇部門の労働者を対象とする。
第2条(休憩の付与方法)
対象労働者については、業務の都合により一斉休憩を行わず、交替制により休憩を与える。
ただし、各労働者に対して法定休憩時間(労働時間6時間超で45分、8時間超で60分)を確実に与えるものとする。
第3条(協定の有効期間)
本協定の有効期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までとする。
令和〇年〇月〇日
株式会社〇〇〇〇
代表取締役 □□□□
労働者代表 △△△△
ポイント
・有効期間(通常1年)を明記すること
・対象部署・職種を限定することでリスクを最小化
・就業規則との整合性を保つ
導入時チェックリスト(影響範囲調査、従業員への説明計画など)
制度やシステムの導入時は、労務・業務・心理的影響の3方向から確認が必要です。 以下のチェックリストを使って、導入時の漏れを防ぎましょう。
導入時チェックリスト
| チェック項目 | 状況 |
|---|---|
| ①昼休憩中の実態調査を実施した(誰が対応しているか) | □ |
| ②法的リスク(違法労働・未払い残業)の確認を行った | □ |
| ③対応ルール・方針を明文化した | □ |
| ④就業規則への追記・改定を実施した | □ |
| ⑤労使協定を締結した(交替制採用時) | □ |
| ⑥社員説明会・ガイドライン共有を行った | □ |
| ⑦システム変更(転送設定、PBX連携など)を設定 | □ |
| ⑧試験運用期間を設け、フィードバックを収集 | □ |
| ⑨対応履歴・休憩補填の記録方法を定めた | □ |
| ⑩定期的な見直しサイクルを設定した | □ |
このチェックを完了して初めて、「制度として運用できるレベル」に達します。
導入後モニタリング指標と改善ループ
制度を導入して終わりではなく、運用後のモニタリングと改善サイクルを回すことが重要です。
主なモニタリング指標
| カテゴリ | 指標例 |
|---|---|
| 労務面 | 実際の休憩取得率(60分確保率)、当番負担の偏り |
| 業務面 | 電話取次件数、留守電・IVR転送率、対応遅延件数 |
| 従業員意識 | 満足度アンケート(「昼休みが確保できている」割合) |
| 顧客対応 | 昼時間帯のクレーム件数・応答率 |
| コスト | 電話代行・システム運用費用の効果測定 |
改善ループ(PDCA)
1.Plan(計画):交替制・代行導入の方針設計
2.Do(実行):試験導入・現場運用
3.Check(評価):定期的な労務調査・アンケート
4.Act(改善):ルール・シフト調整、システム最適化
このサイクルを半年~年1回回すことで、現場の実情に合った運用を維持できます。
まとめ
昼休み中の電話対応は、放置すると労働基準法違反や未払い残業のリスクにつながるだけでなく、従業員の負担増やモチベーション低下の原因にもなります。
本ブログで紹介したポイントを整理すると、企業が取るべき対策は以下の3本柱です。
1.現状の可視化とルール明文化
誰がいつ対応しているかを把握し、就業規則や労使協定で交替制・振替休憩などのルールを明確化。
2.システム・代替手段の活用
クラウドPBX、IVR、電話代行サービスなどを導入し、昼休み中も従業員が自由に休める環境を構築。
3.モニタリングと改善サイクル
導入後も休憩取得率や業務影響を定期的に確認し、必要に応じてルールやシステム設定を改善。
これらを組み合わせることで、法令遵守と従業員満足度の両立が可能になります。
企業は単なる「形だけの休憩」ではなく、従業員が実質的に休める休憩制度を設計・運用することが、健全な労務管理の第一歩です。
カテゴリ: 電話代行